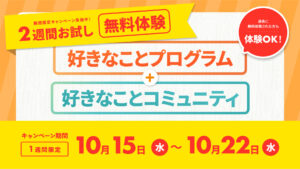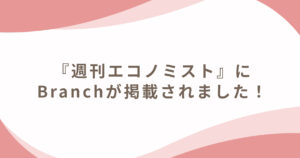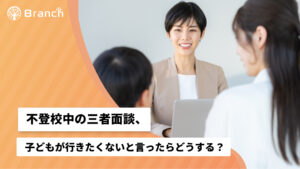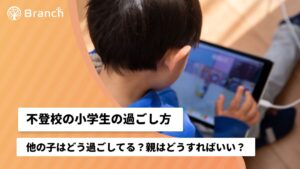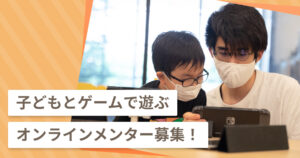こんにちは。不登校や発達障害のお子さんと保護者さんのための居場所、Branchです。
子どもが母親にだけ癇癪を起こすのは、なぜでしょうか。
「この状態がいつまで続くのか」と不安になる気持ちは、多くの保護者が抱える痛みです。
この記事では、小学生の子どもが母親にだけ癇癪を起こす理由と、具体的な対処法としての「取扱説明書(トリセツ)」のつくり方をご紹介します。
メンターや友だちと、安心して「好き」を楽しめる、学校外の居場所。
Branchは、信頼できる大人のメンターと、学校外の友だちと、安心してつながれるオンラインの居場所です。
不登校や発達障害の子どもたちが「好きなこと」を通じて自信がつき、社会とつながることを目指しています。
\メンター2回&コミュニティ2週間&詳細なレポートが無料 /
1. 「なぜ私にだけ?」 母親にだけ癇癪を起こす理由
お子さんが他の人の前では落ち着いているのに、特に母親にだけ激しい癇癪を見せる―
それは決してお母さんのせいではありません。
むしろ、お子さんがお母さんに「絶対的な安心感」を抱いている証拠だと考えられます。
1.1 「関係が切れない」という確信が“甘え”につながる
子どもにとって母親は、どんな自分も受け止めてくれる安心できる存在。
「この人なら感情をぶつけても、嫌われたり、関係が壊れたりしない」という無意識の信頼があるからこそ、外では見せない感情を母親にだけ出してしまうのです。
つまり、癇癪の裏には信頼と安心感(=甘え)が隠れています。
子どもにとって母親は「安心して感情を吐き出せる場所」だからこそ、抑えきれない思いをぶつけてしまうのです。

1.2 声のトーンや言葉がトリガーになることも
一方で、日常の些細な刺激が癇癪の引き金(トリガー)になっていることもあります。
たとえば、母親の声の高さや話し方、特定の言葉が子どもにとって強い刺激になる場合があります。
このようなときは、声のトーンや話しかけ方を少し変えるだけで反応が穏やかになるケースもあります。
2. 癇癪は「いつまで続く」のか? 見通しの立たない辛さへの向き合い方
癇癪がいつまで続くのか分からない――。
その不安は、まるで終わりの見えないトンネルを歩いているような気持ちかもしれません。
2.1 終わりは「ある日、気づけば」やってくる
癇癪には明確な終わりがあるわけではありませんが、多くの保護者が「気づいたら落ち着いていた」と振り返ります。
今は長く感じても、ずっとこのままではないという希望を持つことが大切です。
2.2 低学年では感情のコントロールが未発達
特に小学校低学年のうちは、まだ感情のコントロール力が育っていない時期です。
「楽しい時間が終わるのが嫌」「思い通りにならない」といった気持ちが爆発してしまうのは、発達の途中で起こる自然なこと。「成長の通過点」として受け止めてみましょう。
3. 癇癪を未然に防ぐための「予防」と「トリセツ」のつくり方
癇癪を減らすためには、一つひとつの事例を分解し、家庭で“研究”していくことが大切です。
3.1 母親調べの「トリセツ」で対応を明確にする

「癇癪」とひとくくりにせず、以下のようなポイントに注目し、具体的な行動を記録・分析してみましょう。
- いつ、何がきっかけで癇癪が起きたか(トリガー)
- どうしたら落ち着いたか(クールダウン)
- どれくらいの時間続いたか(癇癪がおさまるまでの時間)
癇癪の原因や対処法は、子ども一人ひとり異なります。
「うちの子にはこれが効く」という、お子さん専用の「取扱説明書(トリセツ)」をつくるつもりで事例を研究していくと、予防策と対応策が明確になり、とても役立ちます。
関連記事
子どもの取扱説明書(トリセツ)作りについては、こちらの記事もご参考にどうぞ
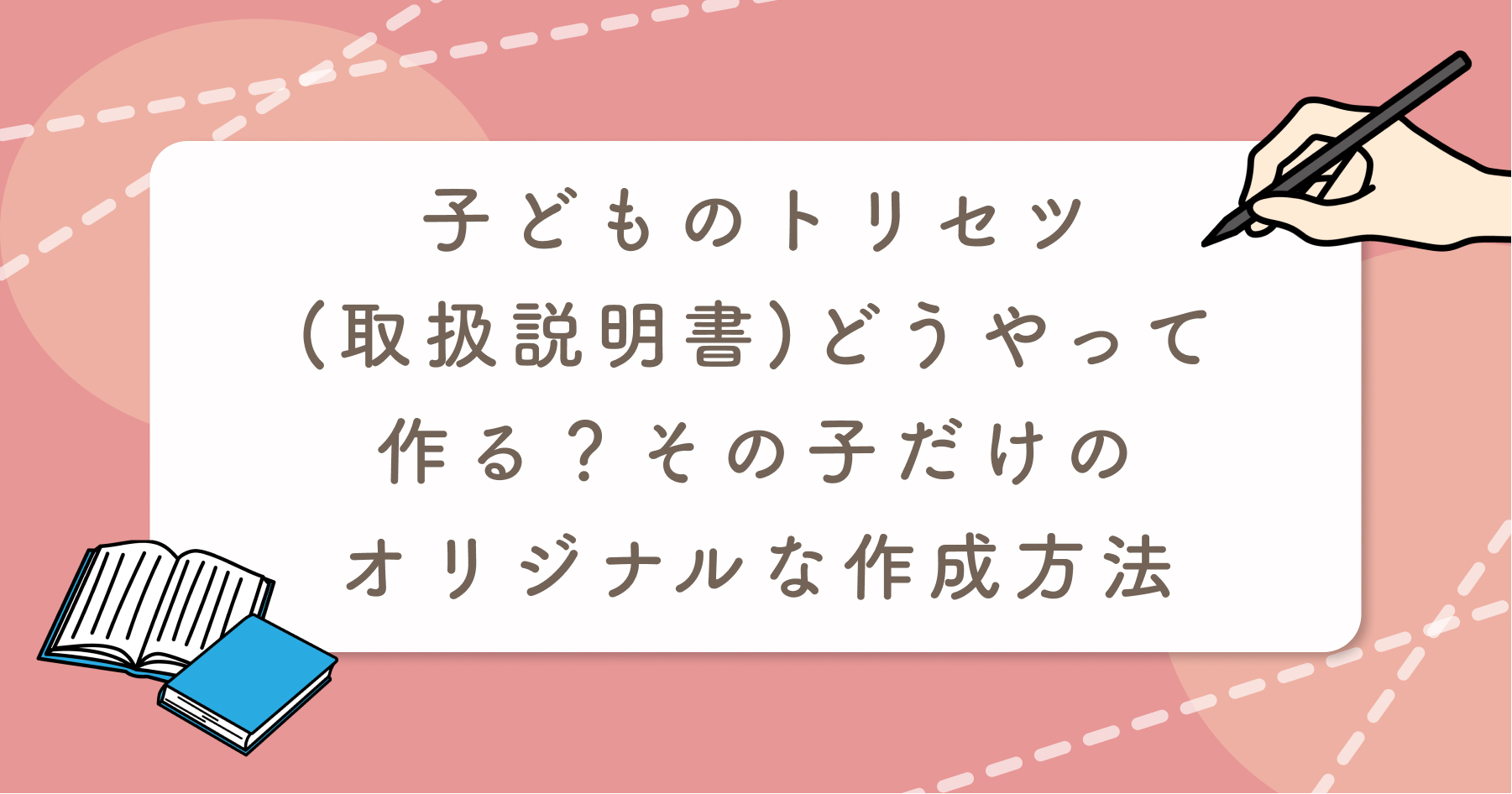
3.2 「トリガー」を避けるための工夫
お子さんが癇癪を起こすきっかけ(トリガー)が分かったら、なるべくそれを避けるようにしましょう。
遊びの終わりなど、切り替え時に癇癪が起きやすい状況では、事前に予告することで見通しが立ち、癇癪を防げることもあります。
声かけの例
• 「何時何分になったら帰ろうね」と具体的な時間を知らせる。
• 「時計の針が5のところに行ったら片付けようね」と視覚的に分かりやすい方法で知らせる。
また、日常の中でお子さんが「満たされている時間」を意識的につくることも効果的です。
心が満たされている状態では、癇癪の頻度が減る傾向があります。
4. 癇癪が起きてしまったときの「クールダウン」と対応法
どれだけ予防しても、癇癪が起きることはあります。
そんな時こそ、落ち着くまでの“型”を持っておくと、親子ともに安心です。
4.1 「クールダウンの型」を“お守り”にする
癇癪時の対応をあらかじめパターン化しておくと、それが親子にとっての安心の”お守り”になります。
たとえば、
「好きな動画を見る」「冷たい飲み物を飲む」「静かな場所に移動する」
など、 お子さんが落ち着きやすい行動をみつけておくとよいでしょう。

4.2 一時的に距離を取るのも立派な対応
癇癪が激しい時は、無理に関わろうとせず距離を取ることも大切です。
状況や相手(たとえば兄弟との口論など)が原因なら、一旦その要素から離れるだけで落ち着く場合もあります。
また、どうにもならないときは、ただ「待つ」という選択も。
強引に動かすよりも、自然に波が収まるのを待つ方が早く落ち着くこともあります。
5. まとめ:癇癪の波を乗りこなすために
子どもが母親にだけ癇癪を起こすのは、母親への信頼と安心の裏返しです。
癇癪のパターンを理解し、トリガーやクールダウンの方法を整理しておくことが、対応を少しずつ楽にしてくれます。
思うようにいかない日もあるかもしれません。
でも、そのたびに気づきや発見を重ねていけば、親子の関係はきっと少しずつ変わっていきます。
無理をせず、自分のペースで、お子さんとの関係を整えていきましょう。
参考記事
子どもの癇癪への対応については、こちらの記事もご参考にどうぞ
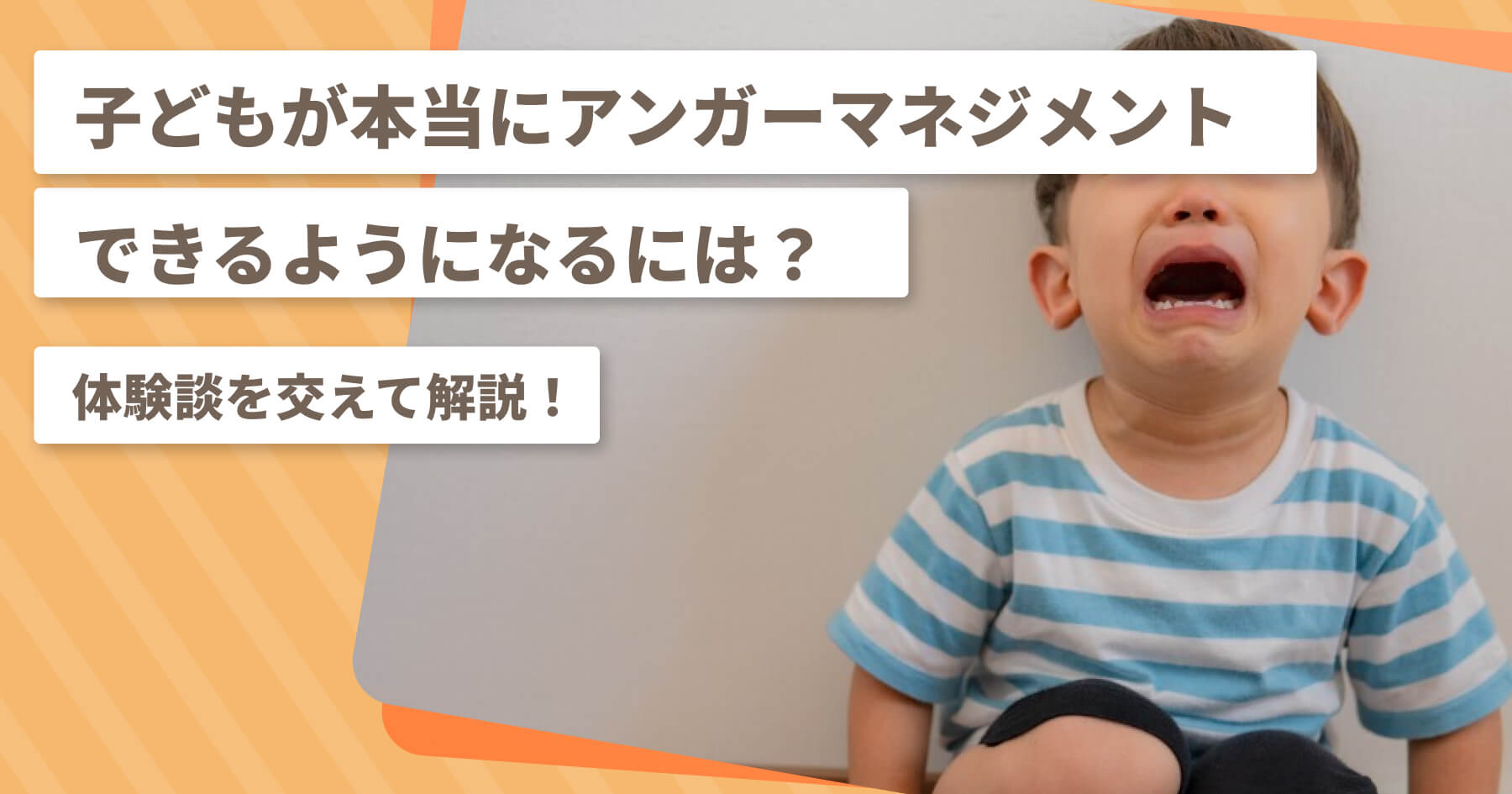
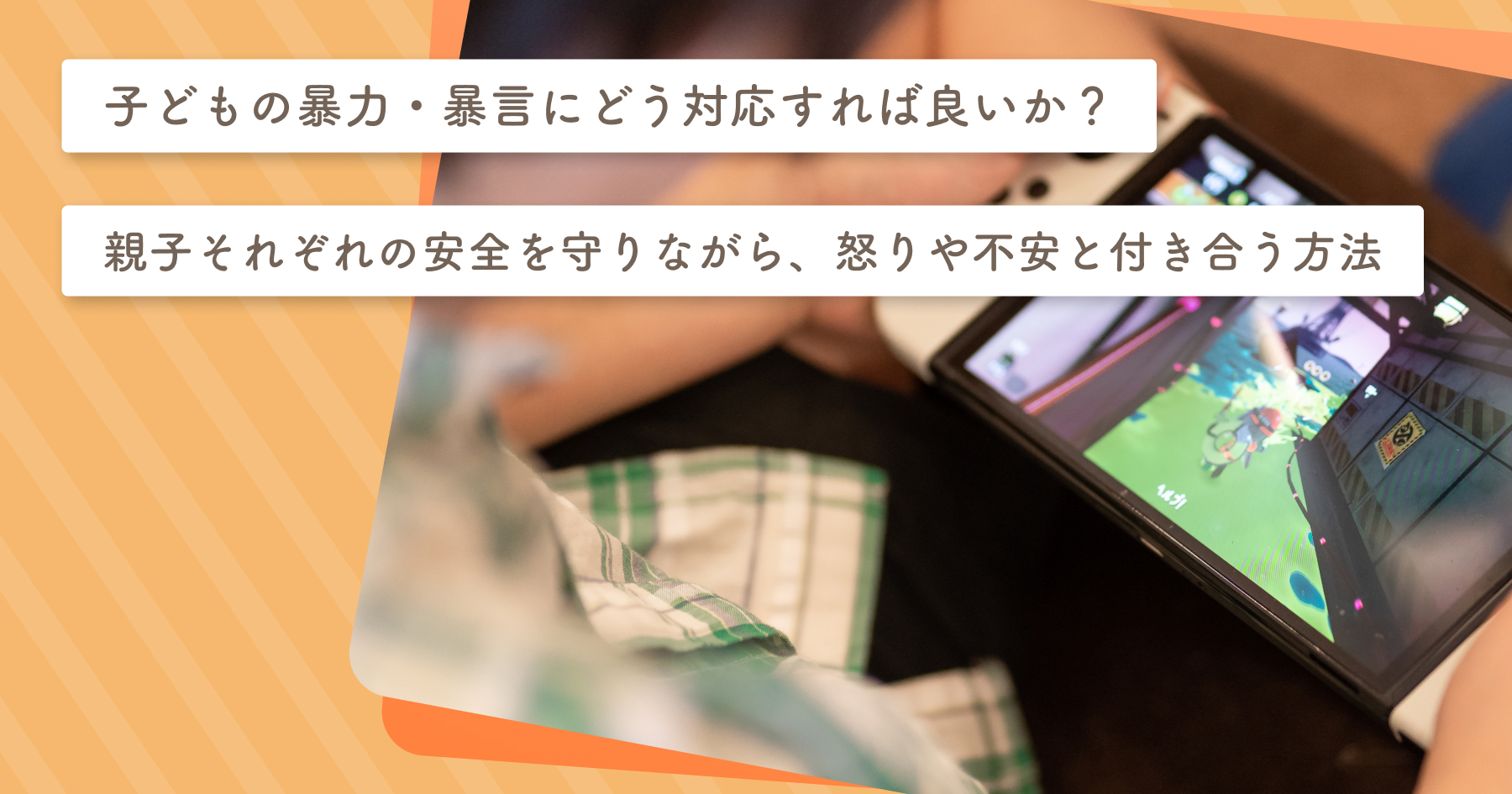
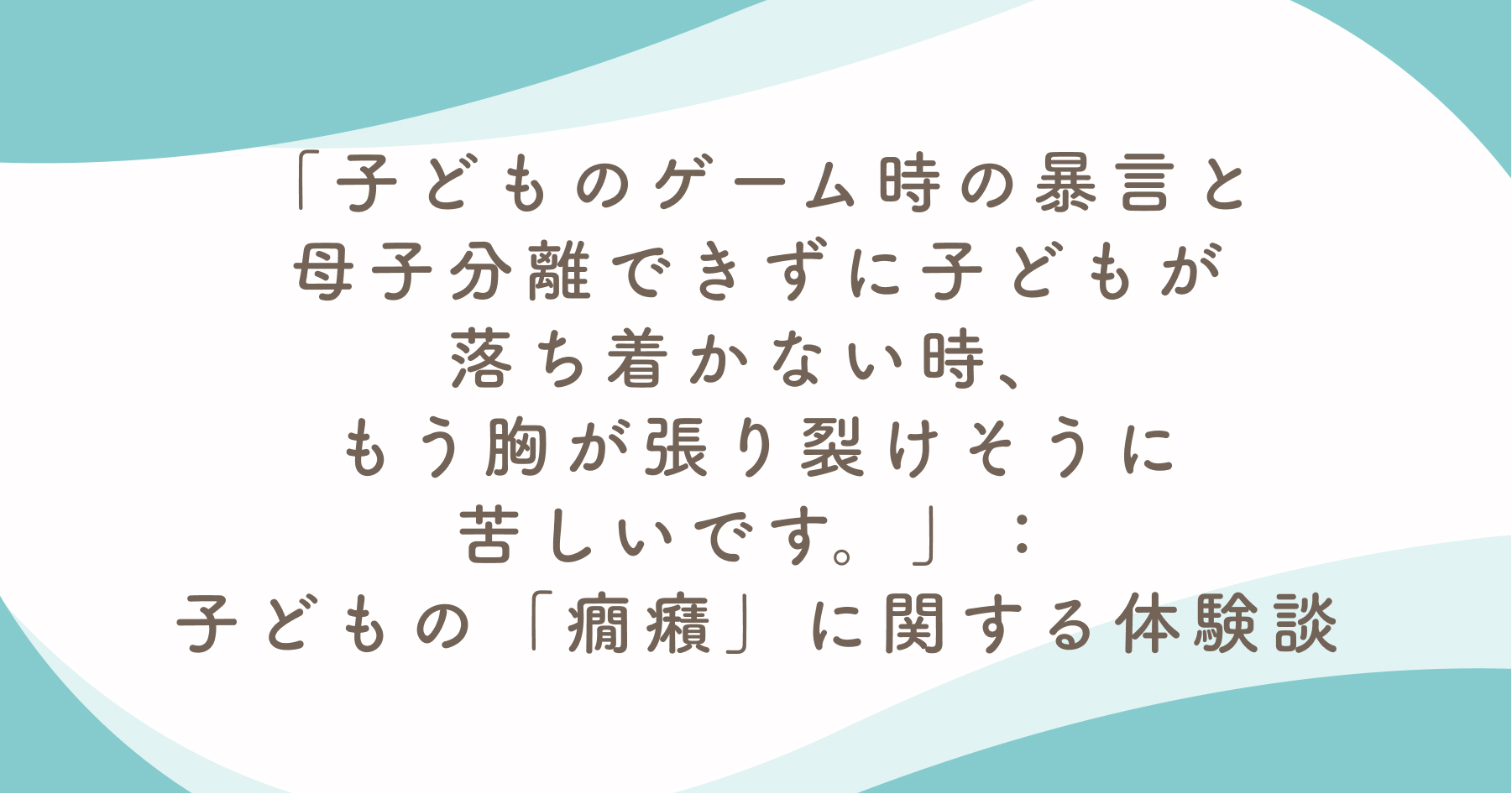
6. Podcastの紹介
この記事は、こちらのPodcastの内容を元に制作しました。ぜひ音声でもお聴きください。
たこやき

不登校経験を持つ息子と娘がいます。Branchでは利用者でもあり、運営のお手伝いもしています。特性豊かな我が子たちと日々過ごす中で、今まで多くの方々に助けていただきました。Branchで絶賛恩返し中です!ゲーム、音楽、マンガ、時代小説、ラジオ好き。
みどり

小学校1年生から不登校の息子がいるお母ちゃんです。Branch利用者であり、運営のお手伝いもしています。息子との旅の計画が、日々の活力!カフェでゆっくりしたり、語学学習、愛犬と過ごす時間が好きです。
中里 祐次

早稲田大学卒業後、㈱サイバーエージェント入社。子会社の役員など約7年勤めた後にサイバーエージェントから投資を受ける形で独立。自分の子どもがレゴが好きで、東大レゴ部の方に会いに行った時に目をキラキラさせていたのを見てこのサービスを思いつきました。好きなことは、漫画やアニメを見ること、音楽を聞くこと、サウナ、トレイルランニング、かなり多趣味です。

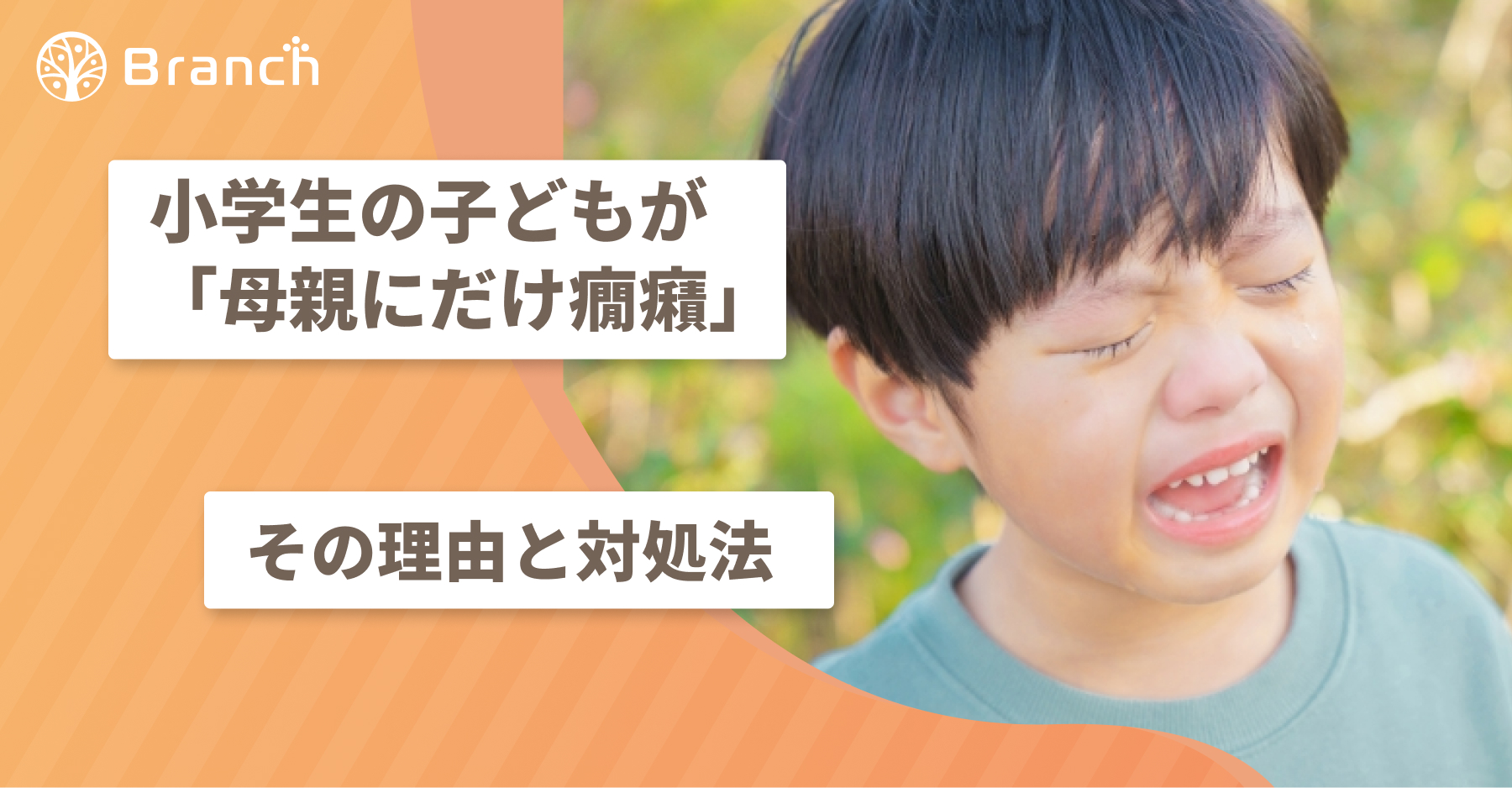
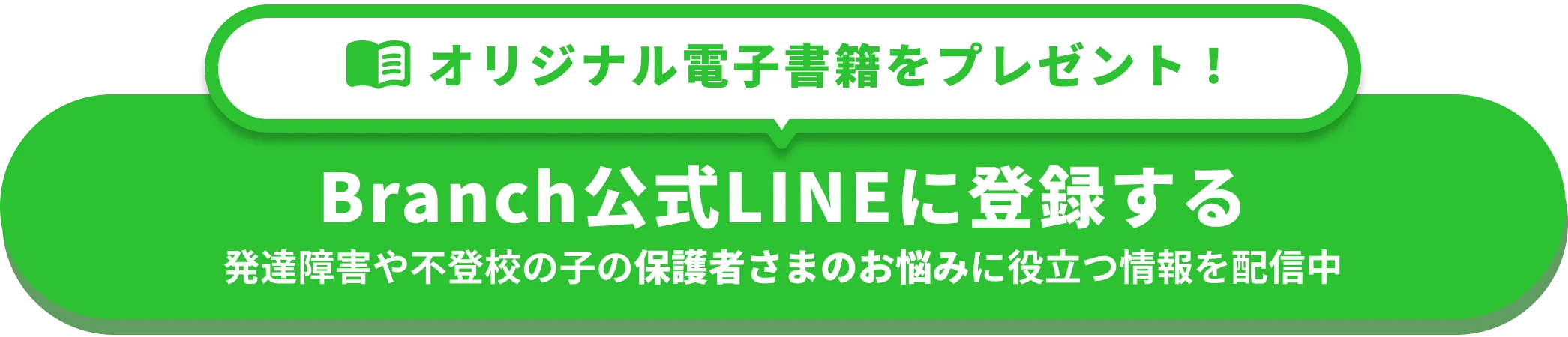


 研修を受け、発達障害の特性にも理解があるスタッフが
研修を受け、発達障害の特性にも理解があるスタッフが 自分の「好き」から 遊べる
自分の「好き」から 遊べる